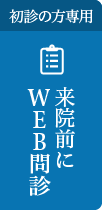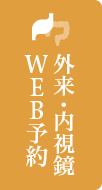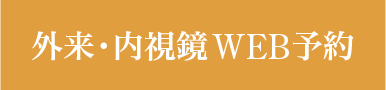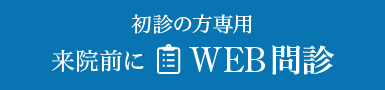日本トップクラスの
専門医が語る、新しい痔の治療
と患者様への想い
 この度、当院に新たな医師が着任いたしました。慶應義塾大学の客員講師も務め、消化器外科・大腸肛門外科の領域で長年最前線を走り続けてこられた壁島康郎(かべしま やすお)先生です。その豊富な経験と、患者様一人ひとりに向き合う真摯な姿勢。先生が目指す医療の形について、お話を伺いました。
この度、当院に新たな医師が着任いたしました。慶應義塾大学の客員講師も務め、消化器外科・大腸肛門外科の領域で長年最前線を走り続けてこられた壁島康郎(かべしま やすお)先生です。その豊富な経験と、患者様一人ひとりに向き合う真摯な姿勢。先生が目指す医療の形について、お話を伺いました。
― 先生のこれまでのご経歴について教えてください。
医師になって以来、大学病院という場で消化器外科医として、主に胃がんや大腸がんといった難易度の高い手術に数多く携わってきました。特に、患者さんのお体への負担が少ない「内視鏡外科手術」を専門とし、技術の研鑽と後進の指導に力を注いできたのが私のキャリアの主軸です。
がんの治療では、手術で病巣を取り除けば終わりではありません。術後のお腹の調子や、排便の悩みなど、QOL(生活の質)に直結する問題にどう向き合うかが非常に重要になります。大腸から肛門まで、人間の「消化」と「排泄」という根源的な機能をトータルで診ることの重要性を痛感し、自然と大腸肛門病学の道へと深く進んでいきました。
これまでの経験で培った最高水準の医療を、もっと一人ひとりの患者様に身近な形で届けたい。そんな想いから、この度ご縁をいただき、町田胃腸病院に着任いたしました。
― 先生が、数ある外科領域の中でも
特に肛門科のドクターとなることを決意された背景をお聞かせください。
排泄という行為は、人間の尊厳に深く関わる非常にデリケートな問題です。多くの患者さんが、誰にも言えない悩みを抱えていらっしゃいました。
専門的な知識と技術で、その方々の悩みを少しでも和らげ、手術前と変わらない、自分らしい生活を取り戻すお手伝いをしたい。そう強く感じたのです。「おしりの悩み」は、命に直結することは少なくても、日々の生活の質を大きく左右します。この分野を極めることこそ、外科医として人々の人生に深く寄り添う道だと確信しました。
― 痔にはどのような種類があるのでしょうか?
大きく分けて3つのタイプがあります。「いぼ痔(痔核)」「きれ痔(裂肛)」「あな痔(痔瘻)」です。
- いぼ痔(痔核):最も多く、肛門の血流が悪くなることで血管がこぶ状に腫れるものです。排便時に出血したり、肛門からイボが飛び出したりします。
- きれ痔(裂肛):硬い便などで肛門の皮膚が切れてしまう状態です。強い痛みを伴うのが特徴です。
- あな痔(痔瘻):肛門の周りに細菌が入り膿が溜まり、最終的に膿を出すためのトンネルができてしまう病気です。
― 何が痔の原因になるのでしょうか?
便秘や下痢、排便時の強いいきみ、長時間座りっぱなしのデスクワーク、体の冷え、妊娠・出産など、原因は日常生活の中に潜んでいます。つまり、痔は誰にでも起こりうる、非常に身近な病気なのです。
― 治療しなければ、痔は自然に治らないのですか?
初期の痔であれば、お薬を使ったり、生活習慣を見直したりすることで改善することも少なくありません。しかし、「たかが痔」と自己判断で放置してしまうのは大変危険です。
症状が悪化して治療が大変になるケースはもちろん、何より怖いのは、その出血や痛みが 大腸がんなどの重篤な病気のサイン である可能性です。専門医が診察すれば、その違いはすぐに分かります。ご自身の安心のためにも、まずは一度、専門医の診察を受けていただきたいですね。
― 痔の手術について、最新の治療法などを教えてください。
「痔の手術は痛い、怖い」というイメージをお持ちの方が多いかもしれませんが、それはもう過去の話です。医療は日々進歩しており、今は患者さんの負担を最小限に抑える様々な選択肢があります。
メスで切るだけでなく、例えばいぼ痔であれば、専用の注射で痔を固めて小さくする 「硬化療法(ALTA療法)」 があります。これは痛みも少なく、日帰りで行うことも可能です。
また、手術が必要な場合でも、私が専門としてきた内視鏡外科の精密な手技を応用し、痛みや出血を最小限に抑え、肛門の機能をしっかりと温存することを第一に考えています。
大切なのは、患者さん一人ひとりの痔のタイプ、症状の程度、そしてライフスタイルに合わせて、最適な治療法を患者様に合わせてご提案することです。
― 実際の手術までの流れはどのようになりますか?
まずは診察で症状を詳しくお伺いし、必要な検査を行います。その結果をもとに、現在の状態と、考えられる治療の選択肢を丁寧にご説明します。手術が決まった場合も、日程や術後の過ごし方など、ご不安がなくなるまでしっかりとお話し合いを重ねますのでご安心ください。
― 先生が痔の手術で最も心掛けていることは何ですか?
二つあります。一つは、当然ですが 「症状の改善」、つまり病気の原因をしっかりと取り除き、再発させないこと。もう一つは 「患者様が快適な生活を送れること」 です。術後も排便機能に一切の問題がなく、これまで通りの快適な生活を送れること。この二つの両立に、外科医としての全技術を注ぎます。
そして何より、患者さんの「怖い」「恥ずかしい」というお気持ちに寄り添うこと。手術という非日常的な体験を、少しでも安心して乗り越えていただけるよう、コミュニケーションを大切にしています。
― 相談しづらい方も多いと思いますが、受診の目安はありますか?
- 排便の時に血が出る
- おしりが痛い、かゆい
- 何かが出ている感じがする
- 下着が汚れる
こうしたサインが一つでもあれば、それは体からのメッセージです。「これくらいで病院に行くなんて…」とためらう必要は全くありません。むしろ、症状が軽いうちにご相談いただけた方が、治療の選択肢も多く、体への負担も少なくて済みます。
― とはいえ、特に女性は受診のハードルが高いと感じるかもしれません。どのような工夫をされていますか?
お気持ちは非常によく分かります。当院では、プライバシーに配慮した空間づくりはもちろん、女性の患者様が安心して心を開ける環境を整えています。
私自身、多くの女性のがん治療にも携わってまいりました。女性特有のデリケートなお悩みや、ライフステージに合わせた体の変化についても深く理解しておりますので、どうぞ安心してご相談いただければと思います。
― 実際に治療を受けた患者さんからは、どのような感想が聞かれますか?
やはり一番多く、そして我々にとって一番嬉しいお言葉は 「悩んでいたのが嘘みたい。もっと早く来ればよかった」 ですね。長年、旅行や温泉に行くのをためらっていた方が、治療後に「今度、孫と旅行に行くのが楽しみなんです」と笑顔で話してくださった時は、本当にこの仕事をしていて良かったと心から感じました。
また、デスクワークが多く仕事に集中しきれないと悩んでいた方が、治療後に「不快感が消えて、仕事への集中力が全く変わりました」と晴れやかにご報告くださる時は、お力になれて本当に良かったと実感します。
― 先生が診療を行う上で、最も大切にされていることは何でしょうか。
「対話」 です。患者さんのお話をじっくりと伺い、病状だけでなく、その方の生活背景や価値観まで理解する。そして、専門家として最善の道をいくつか提示し、ご本人に納得して治療法を選んでいただく。このプロセスを何よりも大切にしています。
私が治すのではなく、あくまで主役は患者さんご自身。私はその方の人生がより快適で豊かなものになるよう、専門家として伴走するサポーターでありたいと思っています。
― 最後に、受診を考えている患者様へメッセージをお願いします。
おしりの悩みは、一人で抱え込まずに、ぜひ一度、私たち専門家にご相談ください。 これまで培ってきた知識と技術のすべてを活かして、患者様の診察・検査を行っております。
おしりのお悩みで病院に行くのは少し勇気がいるかもしれません。しかし、その一歩が、明日からの生活を大きく変えるきっかけになるはずです。患者様のその勇気を全力でサポートしますので、どうぞ安心していらしてください。